
日本人の多くは無宗教?冠婚葬祭や年中行事等、生活に溶け込んだ日本の宗教をご紹介。
日本人は神道?あるいは仏教?それともあるいは、無宗教でしょうか?日本人は、実は信心深い?海外の方に聞かれたら、なんてお答えすればいいでしょう。
<もくじ> 1.はじめに:日本人は無宗教?それとも神道?あるいは仏教徒?外国の方に聞かれたとき、どう答えればよいでしょうか。 ESSAY:皆並んでニコニコと。七福神は、世界の神様の見本市?! 2.神道【SHINTOU】日本人は、生まれながらに全員神道の信者です!日本神話は、日本の建国物語! 3.仏教【BUKKYOU】日本仏教は、大きく分ければ7種類!「南無阿弥陀」と「南無妙法蓮華経」の違いって? 4.儒教【JYUKYOU】学校で、会社で、今に息づく儒教の教え。如何に生きるか、という宗教というよりは哲学です。 5.<COMING SOON> 道教【DOUKYOU】・キリスト教・ユダヤ教・イスラム教など 6. <COMING SOON> GOLDFISH FRIENDLY TOURS 「日本仏教の見本市!寺町めぐり」など
1.はじめに:日本人の宗教について。神道?仏教?キリスト教?それとも無宗教?海外の方に聞かれたとき、どんな風に答えればいいでしょうか。
日本人は、生まれながらに全員がどこかの地元の神社の氏子となる、神道の信者(シントイスト)です。
それと同時に、日本人の多くは生まれながらにどこかのお寺の檀家となり、自動的に仏教徒(ブディスト)でもあります。
「神道信者の人口と仏教信者の人口を合わせると、日本の人口よりも多くなる」と言われるゆえんです。

日本の典型的な家屋には、普通神道の神棚と仏教のお仏壇の両方が置かれています。
「和を以て貴しと為す」と聖徳太子が言ってから、日本は宗教をも和する国に。
仏教が日本に入って来た頃は激しい崇仏論争がありましたが、聖徳太子が「和を以て貴しと為す」と仰ってから、日本は幾度もの神仏習合などのせめぎあいを経て、神仏が共存する国となっています。
聖徳太子(しょうとくたいし)の時代になると、それまでの神道(しんとう)と、大陸から新しく入って来た宗教である仏教(ぶっきょう)が対立し、仏教派が勝利(しょうり)しました。また、日本には仏教と同じ時期に儒教(じゅきょう)も入ってきましたが、聖徳太子はこれも共存させる方針をとりました。
聖徳太子は、これまでに7度もお札になりました。日本で一番お札に描かれたことが多い人です。それだけ日本にとって重要な人物であると言えるでしょう。

その後、聖徳太子は自ら定めた憲法十七条の中で「和を以って尊しと為す」とし、皆が調和することを促しました。
これらの宗教は幾度かのせめぎ合いを経験しながらも一部では交わりあいもしながら、日本では現在も神道と仏教、儒教が共存しています。

これは先述のとおり神道と仏教が習合したからであり、一方が一方を破壊しつくすということがなく共存しているからでしょうが、一神教の国々からすると信じられないことなのかもしれません。
実際はキリスト教の「ゴッド」、イスラム教の「アッラー」、ユダヤ教の「ヤハヴェ」は元々同じ神様(この世界を造りたもうた創造神)で、これらは皆いわば兄弟宗教なのですよね。
ちなみにこの創造神は、仏教では「大日如来」、神道では「天御中主命(アメノミナカヌシノミコト)」と呼ばれます。
またインドのヒンドゥー教では「ブラフマー」という創造神がいますが、彼が目覚めてから眠るまでの時間がこの宇宙の寿命と同じという非常に壮大な神様だそうです。
死後の世界を扱うのが宗教であるならば、現象はひとつです。その山をどこから登るか、どこまでどのようにして登っているか、の違いだけなのでしょう。
なお日本の七福神では、インドと中国と日本の神様がみんな仲良く並んでニコニコと笑っています。
ESSAY:日本は、宗教をも和する国?!七福神は、世界の神様が皆んな並んで笑っています。
●大黒さまは、日本神話の重要人物である「大国主命(おおくにぬしのみこと)」と、インドのヒンドゥー教の「シヴァ神」が習合しました。大きな袋を担ぎ、手には振れば欲しいものが何でも出てくるという打ち出の小槌を持っています。 ●恵比寿さまは、唯一の日本出身の神さまです。大きな鯛を抱え、釣り竿を持ってにこにこと笑っています。日本神話でイザナギとイザナミの間に生まれた最初の子供でしたが、手足も顔もなかった為に葦の小舟で川に流されてしまったのが後に祀られるようになったといいます。 ▶ESSAY:最近恵比寿様を見ると、おいたわしやと涙が出そうになる理由…。日本神話に表れる「恵比寿・大黒や弁天様」の秘密とは? ●弁財天は同じくインドのヒンドゥー教の「パールヴァーティー」という女神と日本の「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」の習合と言われます。琵琶を持ち、芸能の神様と言われます。 ●毘沙門天は、ヒンドゥー教の神クベーラが仏教と習合し、仏教の一種である密教の守護神の一人になりました。 ●寿老人は頭の長い道教の仙人です。南極老人と混同されることもあります。 ●南極老人は頭に頭巾をかぶり、鹿を連れ、手には巻物の付いた杖や桃を持っている道教の神様です。天下が治まり平和な時に表れる南極星を司ると言います。 ●布袋さまは中国が宋の頃に実在した禅宗の僧侶で頭多袋を担いで托鉢に廻り、冬でも薄着でお腹を出す風貌で、一度会うと又会いたくなる純粋で魅力的な人物で弥勒菩薩の化身であると言う人もあったそうです。
2.神道【SHINTOU】日本人は全員、生まれながらに神道の信者です。赤ちゃんが生まれた時や結婚式など、おめでたいことは神社でお祝いします。
日本人は、本人たちが意識しているかどうか別として、全員「神道」の信者です。
日本人が生まれると、自動的に近くの神社の「氏子(うじこ)」になり、お祭りに参加したりします。新しい土地に家を建てる時は、神主(かんぬし)さんにお祓(はら)いをしてもらいます。結婚式も、神社で挙げる人が多いです。
また赤ちゃんが生まれると、神社にお宮参りに行きます。三才、五才、七才の「七五三(しちごさん)」という行事でも、神社にその年まで無事に育ったことのお礼に行きます。
神道【SHINTOU/SHINTOIZM】
日本は、もともと神道の国です。
縄文時代からアミニズム(自然崇拝)の国であったと言われます。
「世界宗教」と「民族宗教」
仏教やイスラム教は、世界中どの民族や国でも信者となる「世界宗教」、神道やユダヤ教はその国や民族のみが信仰する「民族宗教」と言われることがあります。
この世の全てのものに魂が宿るとし、太陽、山、火、水などの自然や、大岩、大樹など通常でない畏敬の念を起こさせるもの。果ては竈(かまど)の神様やおトイレの神様までいると言われてます。
更に特徴的なのは、時に人間までが「神様」になってお祀りされることでしょう(徳川家康の日光東照宮、菅原道真の天満宮、英霊をお祀りする護国神社など)。
神道でいう「神様」は、キリスト教やユダヤ教、イスラム教など一神教の神様とは性質が異なると考えられます。
一神教の神様は、この世界を創造された「唯一絶対」の存在です。神道の中にもそういう性質を持つ神様はいらっしゃって、「天御中主命尊(あめのみなかぬしのみこと)」と言われますが、古事記の最初の方に名前が登場するのみで、本文の中には現れません。
神道の教義は「古事記」「日本書紀」です。
神道(やその他の多神教の宗教)には、多くの神々が登場します。
逆に、人が亡くなったときは、お葬式は仏教のお寺であげます。
四十九日(しじゅうくにち)、一周忌(いっしゅうき)、七回忌(ななかいき)など、亡くなった後の儀式である法要(ほうよう)も、仏教式です。
COLUMN:日本仏教は、大体6つに分けられます。「南無阿弥陀仏」と「南無妙法蓮華経」の違いとは?
GOLDFISH TOUR:沼垂「寺町(てらまち)」は日本仏教の見本市!色んな宗派が揃っています。<COMING SOON>
日本人は、生きている間は儒教(じゅきょう)の影響も大きいといえるでしょう。
会社の社訓などは儒教に基づいていることが多いです。学校の教育も、先生をうやまう文化などは、儒教の影響が大きいといえるでしょう。「道徳」という学校の授業は、「道」や「徳」を説く儒教の教えに基づいているものといえます。
また、道教の仙人のような生き方に憧れる人もいるようです。「山奥にこもって、霞(かすみ)を食べて生きるような…」「太公望(たいこうぼう)みたいに一日釣りをして過ごしたい…」
COLUMN:最近も映画になった「二宮尊徳(にのみやそんとく)」は、どんなことをした人?
他にも、大晦日(おおみそか)は除夜(じょや)の鐘を突きにお寺に行き、年があけてお正月には神社に初詣(はつもうで)に行きます。これらを年をまたいで一度に行うことを「二年まいり」といいます。
GOLDFISH TOUR:金魚亭の二年参りツアー!除夜の鐘、年越しそばからの初詣、お節料理、お雑煮など。日本の伝統的な年末年始を過ごしてみよう♪
紅白歌合戦も忘れずに。
神社とお寺の見分け方
日本には、どの市町村にも多くの神社やお寺があります。
(時々混同される事もありますが)ご存知の通り、神社は神道、お寺(寺院)は仏教の建物です。
見分け方
・鳥居があり、簡素な神殿造り等の建物の奥に鏡などの神器が祀られ、手や口を清める手水鉢があり、注連縄(しめなわ)が結界として張られ、「神主(権禰宜、禰宜)さん」や「巫女さん」がいて「祝詞(のりと)」があげられるのが神社。
・重厚な唐破風などの屋根の建物の本殿に仏像が安置され、宗派によっては座禅堂や鐘突き堂があることもあり、お墓が並び、「お坊さん」や「ご住職」が「お経」をあげるのがお寺。
現代では、おめでたいこと(赤ちゃんの誕生や成長のお祝い、結婚式など)は神道式で、神社で。
お葬式や三回忌、七回忌ら亡くなった方の法要などは仏教式で、お寺で行われるという棲み分けがされています。
儒教は春秋戦国時代に孔子が教えた哲学です。
徳のある人物が天に味方され、自然に王となるという「徳治主義」を説きます。日本では江戸時代に特にさかんになり、「目上の人を敬う」態度や「勤勉」などと共に学校教育や社訓、社風などに息づいており、日本人の倫理観に今なお影響を与えているといえるでしょう。
神様も仏様も一緒におまつり。神仏習合の日本。
日本では、神社に仏教の神様が祀られていたり、仏教の神様が神道の神様もかねていたりします。
日本の宗教は神道と仏教、時々儒教で大体説明できる!?
神道編:
日本人がきれい好きなのは神道が「清(きよ)める」ことを大切にする文化だから。
またお風呂に入るのも、神道の「禊ぎ(みそぎ)」の文化からと言われます。
仏教編:
日本建築の様式で、例えばシンプルな和室や石庭には、仏教の中でも禅宗(ぜんしゅう)が大きな影響を与えています。
池のある庭などは、同じ仏教でも浄土宗の影響があります。
昔から多くの日本人は、亡くなったらあの世(極楽、あるいは地獄)に行くと信じてきました。
江戸時代の日本人が現世を「浮世」と言ってあの世に行くまでの一瞬の通過点だと考えたのも、仏教の影響といえるでしょう。
もっと詳しく↓ COLUMN:「侘び寂び」とはCOLUMN:日本文化のキーワード。平安時代の「もののあはれ」、室町の「幽玄(ゆうげん)」、江戸の「粋(いき)」。そして現代は「かわいい」!
日本人は無宗教だと自覚している人も多いと言われますが・・・。
日本人の中には、自分のことを無宗教だと思っていらっしゃる方も多いようです。
しかし、実際はこのように無意識に生活の中で様々な習慣や年中行事、ものの考え方を通して自然に多くの宗教の影響を受けているのです。
なお、キリスト教の方々からすると宗教を持たない人々が何を善悪の基準にするかわからないからと、不安に思うことがあるようです。
しかし日本の場合は特に信心深い人々ではなくとも一般的に「悪いことをすると地獄に行くよ」「嘘をつくと閻魔(えんま)さまに舌を抜かれるよ」と子どもに言い聞かせたりすることがあります。
また儒教的な「天」という考え方がより庶民的になった「お天道(てんとう)さまが見ているよ」という言い方もあります。
あるいは神仏ではなく、身近に関わる人間たちで構成する世界である「世間(せけん)」がお互いの行動の規制や、監視役になっていたりもします。
高度経済期には商業重視の中で「お客様は神様です」という言葉も生まれました。
このように様々な宗教や思想の影響を受けながら、いわゆる「民度が高い」と世界的にも言われる日本人の性質が形作られているのでしょう。
現代の日本人は、どちらかというと宗教はこわいもの、危険なものという考えの人も多いようです。これは、明治時代に神道が軍国主義と結びついて戦争の強化に利用されたからでしょうか。
また新興宗教で、お金を貢がされたり、殺人事件に発展したり、危ない事件もあるからでしょう。実際に、高額のお布施を要求したり、そのために家族から切り離して洗脳しようとする宗教、強引な勧誘につながるノルマなども問題になることがあります。
古来の神道に外来の仏教、「和を以て貴し」となす。
生まれた時は神道でお宮参り。亡くなるときは仏教でお葬式。
結婚式はキリスト教。教育は儒教。
七福神は様々な国の神様が全員並んでにこにこ仲良く並んでいます♪
1日本人は生まれたら、全員神道の信者!
日本人は、無宗教?信仰心があまりないと言われますが、本当にそうでしょうか?
明治維新で、神道は軍国主義と結びつきました。それで、宗教=怖いもの、というイメージが残っているのではないでしょうか。
日本の仏教は、大体6つに分けられる!
「南無阿弥陀仏」と「南無妙法蓮華経」の違いは?
では、主に
●誕生や結婚式、新年などのお祝い事や慶事に関することは神道、
●お葬式や法事などの弔事や大晦日などに関することが仏教にと棲み分けられています。
お祭りや年中行事も、
●神道由来の初宮参りや初詣、七五三、神社で行われる春祭り・秋祭り
●仏教由来の特定の仏様と縁を結ぶ縁日、盆踊り、などに分かれています。
夏越しの祓えの茅の輪くぐり各神社では、様々な農耕の節目に豊作を祈る新嘗祭、例大祭などが行われている。
その他・家を新築する時・新しい車を購入した時・厄災がふりかかりやすいという厄年など、ことある毎に神社でお祓いを受けることがある
葛飾柴又の帝釈天と縁を結ぶ縁日だよ♪
「二年参り」は、大晦日にお寺で除夜の鐘を突いて年が明けたらすぐに神社に初詣に行くことを言いますね。
お彼岸は、祖先信仰の祖先参りと仏教の彼岸という思想が結びついた日本独自のもののようです。
さらには仏教と同時期にもたらされ、江戸時代に幕府に用いられ広まった儒教も、今現在でも学校教育や会社の社風に影響を与えています。
しかし第二次世界大戦の敗戦を受け、どこか神道などの宗教は人々をひとつにまとめようとする宗教はこわいものという考えが起こったように思います。
このように様々な宗教の影響を受けながら、それらは生活の中に思想や行事として溶け込んでいるので日本人は自分がどこかの宗教に属していると思わないことも多いです。
戦後は高度経済成長の中で「お客様は神様」になったある意味商業が宗教になった時期もあります(笑)。
何か目にみえないものにも感謝する「おかげさま」、「悪いことをすると地獄に堕ちる」「神様、仏様お助け下さい」
世界から称賛される安全性や地震や災害時など助け合いの精神は、日本人のDNAに根底に深く根をおろして刻まれたそれら宗教の教えもであるのではないでしょうか。
・夏越しの祓(一年の真ん中の6月30日に神社に誂えられた茅萱で作った茅の輪をくぐって残り半年分の無病息災を祈る)
・
仏教→
・お葬式(亡くなると僧侶がお経をあげ、故人と親しい人々が集まってお見送りをする)
・法事(初七日、四十九日、一周忌、七回忌などに、お亡くなりになった方の冥福を祈る)
・春彼岸、秋彼岸(あの世とこの世が近くなる春分の日と秋分の日にお墓参りをする)
・お盆(八月十三日~十五日の間にお墓参りに行き、帰ってくるご先祖さまの祖霊を自宅にお迎えする)
・盆踊り(夏祭りで先祖の霊と一緒に踊り、再びあの世に送り出す)
・春祭り(お釈迦様のお誕生日にお寺で生まれたばかりの仏陀の像を花で飾り、甘茶をかけてお祝いする)
・大晦日(一年の最後の日にお寺で除夜の鐘を突いて煩悩を払う)
その他、神仏習合で神道の神様と仏教の仏が合わさった無数の神仏のそれぞれの縁日があり、出店が出るお祭りが行われたりします。
またお寺によっては、僧侶による法話が行われるので檀家の人々が定期的に集まる地域があります。
仏教と同じ頃に入ってきた孔子が唱えた儒教も、実は学校教育や会社の社訓などで我々日本人の考え方にかなり大きな影響を与えていると言えます。
仙人や不老不死などの境地を目指す、老荘思想の存在もあります。
日本では現在信仰の自由が保障されており、様々な宗教の信者がいらっしゃいます。
戦前、戦中に国家神道が軍国主義の教義になったからか、日本人の多くが「宗教はこわいもの」というイメージを持っているように思うことがあります。
しかし毎週教会に通うような形ではなくとも、このように日本人の生活や年中行事、ものの考え方などには多くの宗教が溶け込んでいるのです。
高度経済期には「お客様は神様です」と言われたり、「世間様」が神様のように重く思われたり。
古来の八百万の神々に加え、様々な世界宗教が流れてきて和して、生き続ける日本。
▶ESSAY;「七福神」は、世界の神様の見本市!?みんな並んでニコニコと(^^)
自分が特に信仰を持たない無宗教だと思っている方が少なくない中、災害時などに略奪も混乱もなかったり、女性が一人で夜道を歩けるくらい安全であるなど、海外から「民意が高い」と驚きをもって高く評されることが多い日本人の精神性の理由は、こういった所にもあるのかもしれません。
次からは、それぞれの宗教の特質について見ていきましょう。
2.神道【SHINTOINSM】
日本人は生まれながらに地元の神社の氏子であり、自動的に神道の信者であるといえます。仏教が大陸からもたらされる以前から、「自然崇拝」「太陽信仰」などと共に信仰されていました。
(1)日本神話の基本について
(2)年中行事と関わる神道
(3)現在の皇室について
(4)おうちで神様をお祀りする神棚
3.仏教【BUDDHISM】
日本人の多くは神道であると同時に、どこかのお寺の檀家に属する仏教徒です。
神道は日本人だけの民族宗教ですが、仏教は世界中に信者がいる世界宗教です。しかし日本の仏教は長年の間に独自の進化をしており、ここでは理解しやすくするために大胆に5種類に分けてみようと思います。
(1)奈良仏教系/仏教の教えを学問的・体系的に教える、いわば正統派です。(法相宗・華厳宗・律宗など)
(2)浄土系/最も大切なキーワード(というかそれしかない)は、「南無阿弥陀仏」です。南無=帰依します、心から信じます。阿弥陀仏を心から信じます。だから、亡くなった後は阿弥陀仏さまの治める極楽浄土に生まれ変わらせて下さい。(浄土宗、浄土真宗、時宗、融通念仏など)
(3)禅宗系/基本的にひたすら座禅を組み、「無」になることで悟りの境地に至ることを目指します。開祖はだるまさんことインド人の達磨大師、水墨画や茶道、建築様式などにも影響を与え世界に「ZEN」の名で知られています。最近ではスティーブ・ジョブズも傾倒。「公案」という、いわゆる禅問答を行う一派も。(曹洞宗、臨済宗、黄檗宗など)
(4)日蓮系/日蓮が提唱。キーワードは「南無妙法蓮華経」。南無=帰依します。妙なる法である蓮華経を絶対に信じます。法華経は人は皆地下で蓮華の花のようにつながっていること等を説いた最後にお釈迦様が表した究極のお経。(日蓮宗の他、創価学会、立正佼成会などもこちらです)。
(5)密教系/法具を用い、護摩焚きなどの秘法によって仏と直接つながろうとします。「曼荼羅」はこの宇宙を作ったという「大日如来」が中心に描かれ、この宇宙の成り立ちを表わしています。(真言宗・天台宗など)
ESSAY:白い着物で海に入ろうとしている人がいて、その人が唱えているのが「南無阿弥陀仏」だったら「あっ、とめなくちゃ!」と思うけど、「南無妙法蓮華経」だったら「あれ?もしかして修行かも」と思うかもしれないのはなぜ?と問うていた友人がいたので答えます(笑)というかすごい疑問w
その他に、お釈迦様の素朴な教えをそのまま残す部分が多い原始宗教と言われるもの(インドや中国ではすでに失われてしまっていますが)スリランカの仏教などがあります。
3.儒教【JYUKYOU/CONFUCIANISM】
4.その他の宗教



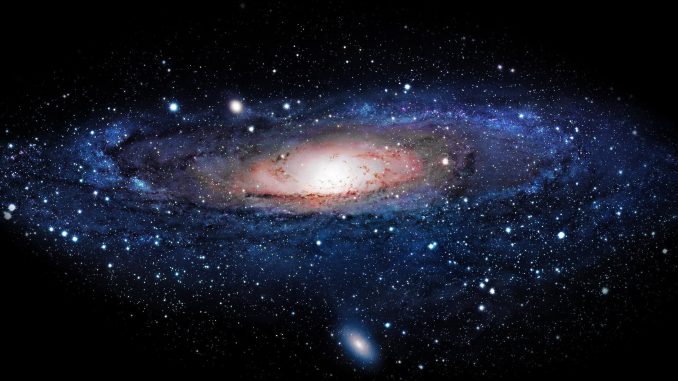
Leave a Reply