
お茶の道は修行の道!?茶道と仏教の一派である「禅宗」にはとても密接な関係があります。
皆さんは、正式なお茶会に参加されたことがありますか。
おごそかな雰囲気で昔ながら型に乗っ取って点てられるお抹茶、
きちんと掃き清められたお庭に、緊張感のあるお茶室。
おしゃべりはせず、きちんと正座をして頂くお客さま。
床に掛けられた一輪の花とお軸には禅の言葉-。
これらの雰囲気は、茶道が仏教の一派である禅宗の影響を
強く受けているからと言ったら如何でしょうか。

お抹茶を頂くうちに、いつの間にか悟りが開けてしまうかもしれません-!?
もくじ: 1.「侘び茶」の開祖は禅僧であり、後に続く千利休などの大茶人も皆、大徳寺から禅の印可(悟った証明)を受けています。 2.仏教の一派「禅宗」ってどんな宗派?臨済宗とは?あの有名な「一休」さんも? 3.村田珠光、武野紹鴎、千利休、数多くの有名茶人を輩出しお茶と関わりが強い大徳寺とは? 4.床の間に掛けられる禅語について。それが今日のお茶会の修行のテーマです!
1.「侘び茶」の開祖は禅僧であり、後に続く千利休などの大茶人も皆、禅の印可(悟った証明)を受けています。
お茶会ははじめの頃、武士達の間で高価なお道具をかけてお茶の産地を当てるギャンブルとして流行していました。
しかし大徳寺から印可を受けた(禅宗において印可を受けるというのは、悟りを得たという証明であるといいます)禅僧である村田珠光が当時の八代足利将軍義政に進言し、お茶会でのギャンブルや飲酒を禁止し、お茶会に精神性を持ち込む「侘び茶」を提唱します。
▶ESSAY茶道:2つの異なる流れ、文化と東山文化。利休VS秀吉、侘び寂びの茶室と金の茶室・唐物と楽焼・利休切腹の真相は・・・?金魚亭的考察とは。
その後に続く茶人である武野紹鴎、あの有名な千利休とその後継者の千宗易、そして今井宗及、津田宗及らの大茶人達は皆、大徳寺から禅宗の僧の印可を受けています(印可というのは、禅宗において禅問答等により師匠から”悟った”という証明を受けることです)。
お茶の儀式が行われ、千利休をはじめ三千家のお墓もあります。
▶ESSAY日本仏教:日本の仏教の一派、「禅宗」ってどんな宗派?ひたすら座禅して雑念を払い、無となることで悟りを目指す。
2.仏教の一派「禅宗」ってどんな宗派?中でも、お茶と関わりが強い「大徳寺」や、あの一休さんで有名な禅問答の「臨済宗」って?
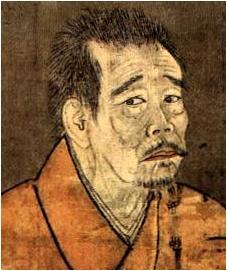
仏教の一宗派である禅宗は、禅僧、禅語、建築、思想、全てにおいて茶道に深い関わりがあります。
村田珠光の師匠であったという説もある大覚寺は、”一休さん”でおなじみの一休宗純も修行した禅宗のお寺です。
一休さんは、実は父親が時の天皇であったのが母親が正妻ではなかった為に世継ぎとなることはなく、寺に預けられたと言います。
「有漏路(うろぢ)より無漏路(むろぢ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」と答えたそうです。
「有漏路」は迷いの煩悩の世界、「無漏路」は悟りの仏の世界だと言います。
今でもお茶室に続く庭のことを路地、または露地と呼ぶのはここから来ているのではないでしょうか。
今私達が暮らしているこの悩みやしがらみやストレスの多い世界から、完成された世界であるお茶室に向かう道であるといいます。
▶お茶会の流れが丸わかり!『金魚亭はじめてのお茶会🔰』
一休はここから師匠に禅の認可を受け一休の道号を授かりますが、一休はその認可を破り捨てます。
全ては空であり、「親に会いては親を殺し、仏に会いては仏を殺す」という程一見激しい言葉もある位、
何物にもとらわれない無の自由な心を目指すため、このような一見奇行と思われる行為の禅僧も多くいめーじがあります。
カラスの鳴く声を聞いて悟ったと言われます。
禅宗というのは特に臨済宗は公案といういわゆる禅問答によって悟りの境地の心に誘導する、あるいは悟ったことを表すのです。
3.
村田珠光は
- さて昨今、「冷え枯れる」と申して、初心の者が備前・信楽焼などをもち、目利きが眉をひそめるような、名人ぶりを気取っているが、言語道断の沙汰である。「枯れる」ということは、良き道具をもち、その味わいを知り、心の成長に合わせ位を得、やがてたどり着く「冷えて」「痩せた」境地をいう。これこそ茶の湯の面白さなのだ。とはいうものの、それほどまでに至り得ぬ者は、道具へのこだわりを捨てよ。たとえ人に「上手」と目されるようになろうとも、人に教えを乞う姿勢が大事である。それには、自慢・執着の心が何より妨げとなろう。しかしまた、自ら誇りをもたねば成り立ち難い道でもあるのだが。
- この道の至言として、
- わが心の師となれ 心を師とするな
- (己の心を導く師となれ 我執にとらわれた心を師とするな)
- と古人もいう。
- 村田珠光のことば
- この道において、まず忌むべきは、自慢・執着の心である。達人をそねみ、初心者を見下そうとする心。もっての他ではないか。本来、達人には近づき一言の教えをも乞い、また初心者を目にかけ育ててやるべきであろう。
- そしてこの道でもっとも大事なことは、唐物と和物の境界を取り払うこと。(異文化を吸収し、己の独自の展開をする。)これを肝に銘じ、用心せねばならぬ。
4.床の間に掛けられる禅語について。それが今日のお茶会の修行のテーマですよ!
お茶会では、お床に掛けるお軸は基本的に禅語、しかも宗派にもよりますが、例えば筆者の習う石州流では大徳寺のものに限るとされています。
そしてその日に掛けられた掛け軸は、その日のお茶会のテーマをあらわしています。
つまり、禅語が掛けられたお茶会ではその言葉の意味や意図をかみしめ、禅の修行をすることに等しいとも言えるのです。
お茶会でよく掛けられる禅語には以下のような物があります。
・喫茶去「きっさこ」:ようこそいらっしゃいました、(まあ難しいことは抜きにして)まずはお抹茶を一服どうぞ、というような意味。初心の者、心得のないものにお気軽にどうぞ、とお茶をすすめる言葉である。
・日々是好日「にちにちこれこうじつ」:雨の日も風の日も雪の日も晴れの日も、たとえどんな日であってどんなことが起こっても、それは良い日であると思う。
・一期一会「いちごいちえ」:今日この日、この瞬間というのはもう二度とめぐってくることはない。同じ人に会うのでも、同じ状況で会うことはない。だから存分に味わい、これが最初で最後と思い大事にしなさいという意味。
・和敬清寂「わけいせいじゃく」:お茶室でお互いに和して、敬い合い、清い場所と精神とでいると、そこには静寂が生まれる。お茶会で味わいたい境地です。
・松無古今色「まつにここんのいろなし」:松の色は今も昔も変わらず緑色のエバーグリーン、不変を表す。
・竹有上下節「たけにじょうげのふしあり」:上の松の語と対になっている。松が不変である一方、人間関係には上下の節(礼節など、守るべきもの)がある。
・花紅柳緑「かこうりゅうりょく」:花は紅く、柳は緑色。自然のあるがままの美しさをたたえた語。さらには、周りをうらやむことには意味がない、という意味も。
・紅炉一点雪「こうろいってんのゆき」:優れた師匠の心は紅く燃え上がる炉のようであり、そこに落ちた雪の一片は、一瞬で消えてしまう。次々に現れる雑念はたちどころに消え去り、常人と違い、二点三点と広がることがない。
・白珪尚可磨「はっけいなおみがくべし」:八珪は最高に完成された美しい玉のことである。それでも尚、磨き続けることが重要であるという語。
・〇(円相)「えんそう」:完全な円によって、宇宙が調和している様を表す。
・本来無一物「ほんらいむいちもつ」:。人間は生まれた時は何も持っておらず、物事を難しく考えることもなかった。あるいは物事は全て空(くう)であるから、執着するべきものは何ひとつない。全てのものは「空(くう)」である、という般若心経にも繰り返し説かれている禅の真骨頂である。
P.S.一方、無一物中無尽蔵「むいちもつちゅうむじんぞう)」:無一物の中にはいくら取ってもなくならない無限の物が含まれている、という禅語もある。執着を離れたところに、全てが与えられるというところだろうか。
・壺中日月長「こちゅうじつげつながし」:中国の後漢書に、ある薬売りの老人が店を閉めたあと、ひょっと壺の中に入り仙境のような素晴らしい世界を楽しんでいたという話がある。無理を言って一緒に壺の中に連れて行ってもらった役人が数日を過ごして帰ると、こちらの世界では数十年も経っていたという。ここから発展して、壺の中のような小さな茶室の空間においても、心豊かに仙境の心持ちで楽しみ暮らすことができるという意味で使われている。
▶お茶会の流れが丸わかり!『金魚亭はじめてのお茶会🔰』



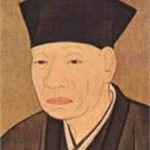
Leave a Reply