
もくじ:
1ユネスコの世界遺産にも登録された、和食の特徴は?日常の家庭料理から世界で大人気の寿司・天ぷら・蕎麦など、ハレの日のご馳走まで。2「一汁三菜」とは?日常を支える、世界からも注目を受ける健康的な家庭の和食をご紹介。
3「会席料理」と「懐石料理」。同じ読みでも異なる世界観を持つ両者をご紹介!
4「薬膳料理」の世界。ベジタリアンやヴィーガンにも新しく注目を集める、究極の健康志向を体現する料理の可能性!
5「はじめての和食」和食デビューに必要な食器、厳選食材、安心安全な伝統調味料などがセットになりました!
1.ユネスコの無形文化遺産にも登録された、和食の特徴は?日常の家庭料理から世界で大人気の寿司・天ぷら・蕎麦など、ハレの日のご馳走まで。
「和食(日本食)」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。
和食【WASHOKU】は、その健康的な栄養バランスや伝統的な季節の美しさなどから、2013年に世界無形遺産登録を受けました。
▶ところで、なぜ「日本食」のことを「和食」と言うの?ふと疑問に感じたあなたはこちらをご覧下さい→
ESSAY:和風【WA-FUU】なぜ日本的であることを「日本風」ではなく『和風』と言うの?「和を以て尊しと為す」日本の文化とは?
和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたのは、
『「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」全体』
であるそうです。
そのため登録の題名は「和食;日本人の伝統的な食文化」となっているとか(農林水産省HPより)。
日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。
和食という特定の食べ物そのものだけでなく、
・南北に長い国土の多彩な食材と、素材を活かす調理技術・調理道具。
・「一汁三菜」を基本とする優れた栄養バランス(「うま味」の活用により動物性油脂が少なくて済む)。
・自然の花や葉などを飾りに用いたり、季節に合わせた器などを利用して季節感を楽しむ。
・日本の食文化はお正月など年中行事と密接で、食を分け合い時間を共有することで家族や地域の絆を深める。
など、その世界観すべてが登録の理由となっているのですね。
日本には、「ハレの日」と「ケの日」があります。
●「ハレの日」は節句や年中行事、結婚式、卒業などといったお祝い事の特別な日。
●「ケの日」は、それ以外の日常的な日々のことです。
正式な和食の形式は、奈良時代や平安時代の節句のための宮中料理である「節会(せちえ)」や、その流れを汲み室町・戦国・江戸時代の武家社会文化によって制定された「五節句」で出される「本膳料理(ほんぜんりょうり)」が元になっています。
日常のケの日の食事で理想とされるのは、「一汁三菜(いちじゅうさんさい)」です。
米飯を中心に汁物(主にお味噌汁)と煮物、焼き物、膾(酢の物など)といった三種のおかずで、栄養バランスを取るのが良いとされています。普段の食事では西洋料理のようにコースで出されるのではなく、それらの料理が同時に食卓に並べられます。「三角食べ」といって、それらを順番に頂くのが奨励されます。
米飯とおかずを同時に食べることで濃い目の味付けのおかずとご飯のハーモニーを味わう、「口中調理」と言われるやり方でよりおいしく頂きます。
お店で出される定食や、お弁当などは、この形が基本となっていることが多いです。
家庭でも、栄養バランスのいい食事として推奨されます。
お正月などハレの日に頂くのは、会席料理です。お正月の「お節(せち)」に代表される複数の品を形式に乗っ取って頂く料理や、
節句などハレの日は、などが出されます。
日本でも本当に正式な場では、(料亭や婚礼、茶事など)順番にお料理が運ばれてきます。
- 先付(さきづけ)・・・ 前菜
- 椀物(わんもの)・・・ 吸い物、煮物
- 向付(むこうづけ)・・・ 刺身、膾
- 鉢肴(はちざかな) ・・・ 焼き物、焼魚
- 強肴(しいざかな) ・・・ 炊き合せ等
- 止め肴 ・・・ 原則として酢肴(酢の物)、または和え物
- 食事 ・・・ ご飯・止め椀(味噌汁)・香の物(漬物)
- 水菓子 ・・・果物
ご飯、止め椀、漬物は同時に供される。ただし上記以外にも油物(揚げ物)や蒸し物、鍋物が出ることがある。油物が供される場合には一般に強肴のあとである。飲み物は基本的に日本酒、または煎茶である。近年はほうじ茶やコーヒーが出されることもある。明治時代以降は肉も出される。シチューなどの洋食の皿が交えられたり、デザートとして洋菓子が供されたり、ご飯の代わりに蕎麦やうどんが出されることもあり、上記のような献立の流れに必ずしもとらわれるものではない。
茶道の心である侘び・寂びを料理として表現しており、「旬の食材を使う」、「素材の持ち味を活かす」、「心配りを持っておもてなしをする」という三大原則を掲げています。
例:一汁三菜の例
※節会(年中行事、節句)
奈良時代の律令制から始まる。元旦(1/1)、白馬(1/7)、踏歌(1/16)、上巳(3/3)、端午(5/5)、相撲(7/7、後に7月下旬)、重陽(9/9)、豊明(11月新嘗祭翌日の辰の日)、釈奠、盂蘭盆会などの節句に宮中行事で供される食事。
※平安時代は元旦、白馬、踏歌、端午、豊明が「五節会(ごせちえ)」として重んじられました。
※室町時代になると幕府が人日、上巳、端午、七夕、重陽を重視する「五節句」を定めました(これが現在でも続いています)。
※本膳料理
一汁五菜、二汁五菜、二汁七菜、三汁五菜、三汁七菜、三汁十一菜。
「式三献」では、「初献に」海月・梅干・打鮑、「二献」に鯉のうちみ(刺身)、「三献」にはわたいり(腸煎り~鯉の内臓の味噌煎り煮)が出されることが通例であるが、これらには箸をつけず、実際に食されることはない。
室町時代から江戸時代の武家で生まれた「式三献」。今でも、「まずは一献」などと客に酒をすすめるのはこの名残でしょう。
会席料理や伝統的には、ケの日の一汁三菜。
懐石料理。四季の旬を大切にすること、ハレの日の節会、米や麦を発酵させて生み出す色んな調味料、素材を活かす生食、出汁(だし)、美しい盛り付けなどが特徴です。
米を炊いたご飯を主食とし、それ以外に汁物、おかずとなる料理を数品頂きます。
日本には、世界各国と同じく食品の中の「人体にとって有用な菌」のみを増やして作る「発酵食品」という文化があります。
日本食に欠かせない「醤油」、「味噌」、「酢」「みりん」などの調味料や「日本酒」、「納豆」などは全て発酵食品です。
最近は、米糀で作る「甘酒」が大人気ですし「塩糀」、「醤油糀」などを使った漬物などの料理を家で作るのもブームです。
食品が美味しくなって、身体に良い。
一汁三菜【ICHI-JYUU-SAN-SAI】
日常的な食事の基本のスタイルは、「一汁三菜(一椀の汁物に三種類のおかず)」と言われます。
それぞれを見ていきましょう。
●一汁【ICHI-JYUU(One Soup)】:
通常は、味噌汁です。味噌は、茹でた大豆に塩を混ぜ、麹菌(小麦で作った良質な菌)で発酵させたペーストです。
まず昆布や鰹節(乾燥させ、発酵させて硬くなった鰹肉のかたまりを削ったもの)をお湯で煮出して、旨味【UMAMI】(アミノ酸や核酸)の抽出された出汁【DASHI】を取ります。
調理師の友人が言ってたんだけど、人間が旨味を感じるのは、アミノ酸(や核酸)だけらしいよ。
ええ~!!
だから多くの和食が、出汁を取るところから始まるのじゃ。
出汁は素材の味を邪魔せずに、旨味を与えてくれる。
和食が薄味でも、美味しい理由だね♪

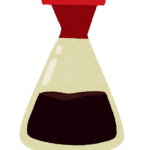






Leave a Reply