
昔の一般の人々が用いた食器たち、「雑器【ZAKKI】」。
江戸・明治・大正・昭和初期、中期ー。
普通ならガラスケースに
入っているような時代のものが、
お手頃な値段で手に入るのが魅力です。
食器として使えばインスタ映えするのはもちろん、
アクセサリーを入れたり
苔玉や観葉植物を飾ったり。
是非、お手元に置いてあげて下さい♪
1.染め付け【SOME-TSUKE】 2.印判【IN-BAN】 3.口紅【KUCHI-BENI】
1.染め付け【SOME-TSUKE】

食器の模様や柄の付け方として、「呉須(ごす)」という中国由来の鉱物を原料とした顔料をひとつひとつに職人さんが手作業で絵付けをしたもの。
色は基本的に青で、淡い水色から濃い藍色、黒色(濃淡の他、酸化コバルトや酸化マンガン、酸化鉄などの成分の分量による)まであります。
豊臣秀吉の頃から日本に入り最初は非常に高価でしたが、江戸時代頃に輸入されて一般的に見られるようになります。
幕末(江戸時代末期)から明治時代になると、ドイツで発明された「ベロ藍」(ベルリン藍がなまったもの)が輸入されるようになり、非常に鮮やかで発色の良い青色が食器や浮世絵などに多用されるようになりました。画家の名前を取って「広重ブルー」「北斎ブルー」、そして日本における印象的な色ということで「ジャパンブルー」とも呼ばれます。

今でもサッカーの侍JAPANのイメージカラーは「SAMURAIブルー」だね。
日本の食器といえばやはり白地に藍色が基本じゃな。どんな色の料理とも合い馴染みやすく、上品に味わい深く「映える」のぅ。
2.印判【IN-BAN】

幕末(江戸時代末期、「天保」頃)から明治時代の初めの頃までの食器類に多く見かけます。
模様が透かしのように入った版に藍色の上記のような染料を刷り込み、食器に絵付けしたもの。


紙版を使ったものは多少模様がズレていたりもするのですが、それもコレクターの間では味わいとして好まれたりもしています。
紙版、同版、粘土版、変わったところではコンニャク版などもあります。
3.口紅【KUCHI-BENI】

お皿などの食器の周りに縁取りがされているものを「口紅」と呼び価値が少し上がります。
薔薇の花を佐賀地方の方言で「棘花(「いげばな)」「棘牡丹(いげぼたん)」と呼ぶように、「いげ」は棘(とげ)の意味。縁がぎざぎざの細かいフリル状になっている印判のお皿のことを「イゲ皿」といいます。
江戸時代後期から大正時代を中心に昭和初期頃まで伊万里や美濃で量産されました。
藍色の印判皿が濃い茶色で、厚みのあるぎざぎざの縁取りと組み合わさり、独特の魅力を醸し出しています。


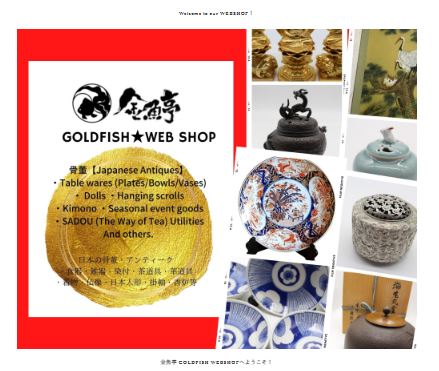
Leave a Reply